Fireside Chat 対談:日本発のイノベーションが世界を変える
シンギュラリティ・ソサエティ BootCamp#2 Demo Dayにおいて、業界をリードする起業家、エンジェル投資家、プロダクトリーダーたちが一堂に会し、グローバル市場を目指す「日本発のサービス・プロダクト」の可能性について熱い議論が交わされました。
このFireside Chatでは、米国での豊富な経験を持つ中島聡氏や、日米で数々のプロダクトを成功に導いてきた森俊介氏をはじめ、田中泰生氏や野本遼平氏といった多彩なバックグラウンドを持つ登壇者が、それぞれの視点から成功の秘訣、戦略、そしてグローバル展開に必要なネットワークの重要性を語りました。モデレーターを務めた矢﨑啓太氏の進行のもと、対談は技術革新だけに留まらず、スタートアップが直面する現実的な課題とその解決策にまで踏み込む実践的な内容となりました。
対談内容
矢﨑:
今日のテーマは、Fireside Chat「日本初のサービス・プロダクトがどのようにグローバルに勝てるのか」という設定ですが、答えを知っているわけではないので、それも一緒に考えられたらと思います。簡単に自己紹介をいただきたいと思います。
森:
森と申します。今は日本でフィンテックの会社でキャッシュレスを進めたりプロダクト全般を見ています。元々高校2年で単身アメリカに行って、高校、大学、大学院とアメリカにいました。その後日本で数年仕事をして、シアトルに移りマイクロソフトで8年ほど、WindowsやIEなどのエンジニアをしていました。次に中島さんとUIEという会社を一緒にやって、その後日本で仮想化の会社に5、6年。再びアメリカに戻り、8年ほどプレPOからIPOくらいのステージの会社、例えばDocusignやメタバースを手がけるROBLOXなどのスタートアップに携わり、3年半前に日本に来た。現在は、メインでプロダクトを作ったり、エンジェルインベスターをちょっとやっている感じです。
中島:
中島です。高校生のときからプロダクトを書いて、マイクロソフトに勤め、二度ほどスタートアップを立ち上げてエクジットもし、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家も経験してきました。現在は主にメルマガを書くことと、シンギュラリティ・ソサエティをやっています。メルマガを書くのはほとんど趣味で始めたんですけど、今、2万5千人の有料ユーザーがいるという、ちょっと異常な状況になってしまって、ビジネスになってしまったなと、引退できないなという状況です。シンギュラリティ・ソサエティでは、現在ブートキャンプという長期的ハッカソンのようなイベントでスタートしたしたものが現在2期目を走っていて、それも、私が言い出しっぺで始めたとはいえ、やる気のある方が集まっていただき、こういうイベントを開催できることになって、感謝しています。 また、GraphAIというオープンソースのプロジェクトを、去年、私はハワイからシアトルに向かう飛行機の中で始めたら、それが結構いい感じで育ち、今日明日と隣の部屋でGraphAIのハッカソンをしています。その流れでこちらに来ていただいている方もいるので、私もいまだにコードを書いています。GraphAIというのは、もともとは非同期のプログラミングを簡単にするためのプラットフォームとして始まったんですけど、実は、AIエージェントを呼ぶのに非常に適しているので、あえてAIという名前をつけて、GraphAIにしました。GraphAIは、グラフを作って、データフローでプログラミングをするという、従来とは異なるる新しい手法です。ちょっととっつきにくい部分もあるかもしれませんが、使いこなせば並列プログラミングに便利なプラットフォームになりますので、ぜひともよろしくお願いします。
田中:
芸者東京という会社の田中と申します。今日ここに座っているのは、カジュアルゲームという分野でかつて、数年前アメリカでAppStoreでランキング一位、グローバルでランキング一位をとって、ゲームが一億ダウンロードされるみたいなビジネスを当てました。その前もずっとゲーム業界にいて、ソーシャルゲームや日本でトップをとったり、ARのはしりの時にプログラムを作っていました。 テクモというところにいて、ビデオゲームとかでアメリカで『Dead or Alive 』とか、『NINJA GAIDEN』というのは、USでいっぱい売れるプロダクトに関わっていたこともあり、その前は実は、エンジニアバックグラウンドじゃなくて、大学の東大法学部で、その後、普通に小さなコンサルティング会社にいました。ひょんなことからゲーム業界に入って、「お前、東大出てるからプログラム分かるんだろう」ってテクモの社長に言われて、やったらちょこっと書けるようになったんで、なんちゃってゲームクリエイターみたいになって今に至ります。その流れで、皆さんのヒントで僕も学びたいなと思ってます。最近AIっていうのもすごいなと思ってて、いろんなAIの活用し方あるんだなって学んで、自分なりにいろいろ勝ち筋、こうやったら行けんのかな、行けないのかなみたいなことを試作してますんで、その辺も今日も勉強できたらと思ってます。よろしくお願いします。
野本:
グローバルキャピタルパートナーズの野本です。VCをやっています。投資先でいうと、AIロボットの会社に投資していて、比較的外貨稼ぎやすいです。また、ゲノム編集の会社にも投資していまして、それは創薬が主戦場なので、必然的にアメリカで勝敗する形になっています。また、歌い手という2.5次元アイドル、アニメーションキャラクターIPを使ってアイドルニートを展開していく会社にも投資していまして、そこはアジアで展開しやすい商売です。ほかにもダイニーというレストラン向けのオンリーワンのクラウドにも投資していて、どちらかというと、飲食店と一緒に外国でも商売したいという話をしていています。比較的外貨と円の両方に関わる投資先が多いので、今日この場に呼ばれているのかな、と感じています。よろしくお願いします。
矢﨑:
それぞれ皆さん、バックグラウンドは違う中で、まずは大きいテーマからお話を伺っていければと思います。日本発のサービスやプロダクトは、どのようにグローバルで勝てるかということです。日本発のスタートアップと海外のスタートアップはすごく大きく違うところがあるので、どういう差を埋めていくと、このコミュニティからYコンビネーターに出て、そこからユニコーンになっていく企業が生まれるのか、ということをお伺いしたいと思います。
中島:
僕はアメリカにいて、アメリカ人と自分でも起業したし、それから周りで起業している人もいるけど、アメリカで暮らしている人って基本的にすごく楽観的で、特にアメリカで生まれて育った人は、実は海外のこととか知らずに、ラッキーなことに英語圏で生まれているし、市場が大きいから、別にアメリカ向けとか世界向けとか考えずに物を作っているんですよ。だから、そんなにグローバル戦略とか持っていないんです。逆に持っていないからこその強みがあるんですよ。日本人は逆に、日本という市場があってそれなりの大きさもあるし、英語がネイティブじゃないということで妙に「グローバルか日本か」みたいなことを意識しちゃっていて、それがマイナスになっている面がすごくあると思います。結局、ネットは世界と繋がっているんだから、あまり市場を意識せずに、何が求められてくるかを狙うのがいいと思います。結局、どこを狙うかによってグローバル向けかどうかが決まるんです。例えば、補助金申請なんていうのは、どう見てもグローバルにはあり得ないんです。日本だけのことなので、別にそれで全然グローバルじゃなくても構わないけど、でも、例えばアニメで行くんだったらアニメは世界で売れるし、ひょっとすると日本にあるコンテンツの強みがあるから海外展開できる場合もあるので、あまり「グローバルで行かなきゃいけない」とかじゃなく、たまたま日本にいるんだから日本のクリエイターのものを海外に出すビジネスができる、という気持ちでグローバルに行くのが、僕としては自然だと思います。
森:
「日本発」っていうのが、どういう意味かっていうと、日本で生まれた人がやれば日本発なのか、日本でローンチしてある程度成果を出したものが日本発なのか、日本でとりあえず会社作れば日本発なのか、いろいろあるとは思うんですけど、私はどちらかというとアメリカで過ごした時間が多いので、確かに日本で作り込んでから外に出すというのは、ハードウェアは別として、ソフトウェアは難しいところがありそうな、もちろん不可能じゃないと思いますが、早めにグローバルに行きたいと思うなら、早めにやるべきだと思います。今、その会社が解決しようとしている問題が日本独自のものなのか、それともユニバーサルなものなのか、もしユニバーサルなものなら、とはいえ日本にいるとなかなかそれが分かりにくいですし、実は出たら違うってことがあるので、早めにそれがユニバーサルなものかどうかを検証した方が、成功確率は上がるんじゃないかなと思っています。それが唯一のソリューションだと思っています。
矢﨑:
そういうの、メタ的な認知能力みたいなところはすごく重要なものですよね。自分がどれだけユニバーサルなものを掴みに行けるか、っていう。
森:
日本に住んでいると、そういうところが分かりにくいと思うので、その場合は実際に乗り込んで、とりあえず披露してみるということで、「全然違うと思うかもしれないし、実は結構行けるんじゃないか」っていう感覚を確かめるのが全然違うと思います。
田中:
ゲームで言うと、僕はプラットフォームを目指している人は本当に素晴らしいと思うんですけど、僕はコンテンツ屋なので、プラットフォームに寄生する側面があって、プラットフォームがなければ、いいものが作れないと感じています。例えば直近のわかりやすい例で言うと、昔、僕がグリーとかモバゲーという日本のプラットフォームでゲームを作っていたとき、両方とも当たったときは、全盛期でマーケットキャップが3000億とか5000億とか行って、一番の会社になればだいたい利益15億くらい出るというコンテンツプロバイダーとしてのモデルがありました。ところが、今やってるカジュアルゲームって実は、プラットフォームがあるわけではなく、アメリカの「AppLovin」っていう会社があって、皆さん、AppLovinって知ってますか?いわゆる、モバイルアプリ向けの広告会社なんですけど、そこは実は、一昨年のNvidia、去年のAppLovinと言われていたくらい、一時期マーケットキャップが20兆まで行ったんですよね。僕は実際、本社にも行って、社長にも会ったことがあります。たかがグローバルのスマホアプリのマーケティングソリューション、つまりカジュアルゲーム広告屋であっても、絶好調のときには当然、そこのプラットフォームに、その広告配信ブランドもぶら下がって、僕らが勝てば、日本で15億だったものが、海外では100億とか1000億とかになってしまうんです。実際、グローバルっていうのは、特に日本からだとアメリカばかり見がちですが、僕たちがベンチマークしている会社、例えば一番有名ではフィンランドのSupercellとか、クラッシュ・オブ・クランとかKuraRowaとか、まあ有名なところもありますけど、例えばロシアの「Playrix」っていう会社、誰も知らないかもしれませんが、そこで売り上げが4000億、利益が1200億とか出ているんですよ。あと、トルコの、もしくはベラルーシとか、ロシアかな、AZUR GAMESとか、それをプラットフォームと見なした場合、僕らからすると「わけのわからん!」って怒られるかもしれませんが、ロシアやトルコにヘッドクォーターがあるようなゲーム会社が、iPhoneやAndroidのアプリ上でビジネスを展開していて、アプリを見るとやたら広告が出る、ロイヤルマッチとか「なんじゃこれ」って感じのものです。要は彼らです。彼らはこっそり、利益が千億円台とか出しているけど、あまり日本のビジネスシーンでは話題にならない。でも、僕はそっちの人たちをベンチマークにしているので、正直、今言っても成功途中であっても、道中で10億単位の利益が出ていて、うまくいけば100億単位、そこまで行けば1千億単位の利益が出るビジネスがある、という事例もあるんです。とにかく、グローバルの定義っていうのは非常に広いんじゃないかと感じます。
矢﨑:
野本さん、起業家の具体的な体験を聞く中で、アメリカだけじゃなく、具体的なエピソードはありますか?
野本:
結果的に、何か稼げそうな事業になったからちゃんと稼げに行く、っていう結果論もある気がしているので、グローバルな事業やりたいから起業するというよりかは、例えばAIロボットの技術を使ってこういうものを作ってやっていきたい、まあそれって別にUSでも同じだよね。話してみたら、普通に向こうから連絡が来て商談が始まったりするので、ソリューションそのものがユニバーサルであれば、結果的にそうなるし、マルチローカルなもので違う国でも展開できるようなものであれば、結果、そうなるっていうイメージではないかと思います。
矢﨑:
一旦、グローバルで勝つということを目的に置いた場合、もしかしたら、世界で通用するデベロッパーあるいは起業家みたいなもののキャラクターって、ある程度不変的に何パターンかこういうマインドセットを持っている人であることが、少なくとも必要条件になりそうな話が出てきそうな気がするんですが、そのあたり、何かイメージはお持ちでしょうか?
田中:
僕は、ゲームの世界で元々任天堂とかソニーのおかげでグローバルな環境にいたんで、それも見てたんですが、最近、とある先輩VCにいろいろ聞いて、一番思ったのは、基本的にほとんどのビジネスが、日本という国の大企業とか、資本主義の成熟度、つまり大企業が非常に無駄の多い構造に放置されているとか、あるいは日本の資本市場っていうのが、ちょっと社会主義的な要素で放置されているから、そこのアービトラージを取りに行っている、という感じです。具体的に言うと、大企業の中の人が本来作るべきものを作れないから、そういうのを外部のスタートアップで作ると、電力会社やガス会社など、高い利潤が保障されているいわゆる日本の大きな会社があるんで、そういうところはNTTドコモとかもそうですけど、社員一人あたり、十分の一も回っていない状態で利益を上げているので、本来その人たちが内部で工夫すれば同じくらいの業務ツールが作れるんじゃないかということを、外からのスタートアップや商品の導入で利益を上げることで、10億単位の利益が出たり、場合によってはマーケットに何百億とかで上場できる、というところが日本にはたくさんあって、それがスタートアップの約8割くらいじゃないかと見えてきたんです。もちろん、そこって、アメリカとか、森さんや中島さんがいる国は、本当の資本主義で、もし無駄が社員一人分でもあれば、いなくても良いんじゃないかって、社員もすぐに解雇されるような社会環境ですから、なかなか、絞れる雑巾が放置されていない国では、本当に価値のあるプロダクトを作らなければならなくなります。それは、別に日本という独自環境じゃないと思っていても、売れるということでグローバルに出れるんじゃないかというのが、僕がこの半年ほどのいち感想です。
中島:
僕がアメリカに行ったのは89年で、マイクロソフトで10年ちょっとアメリカにいたので、その時期というよりもその後かな。やっぱり、i-Modeが日本で成功して、あれって世界で初めてインターネットにつながるモバイル端末だったのに、ものすごいことだというのに、なぜか世界で成功しなかったっていうのを見てたし、あればあれでいろいろ言いたいこともあるんだけど、あとMixiっていう、すごいアプリで、本当に世界初の素晴らしいソーシャルネットワークだったのに、フェイスブックに負けたじゃないですか。負けたのが、僕から見ると、自分から負けに行ったように見えて、というのは、Mixiは割と早々に上場してしまったから、上場して黒字化しなければいけなくなって、ビジネスモデルを固め、かっちり日本でやっている間に、フェイスブックは超赤字を垂れ流しながら、VCから大量のお金を集め、世界制覇に乗り出したっていう。それを横から見て、僕はすごく勿体無いと思ったんですよ。で、結果として言えば、早く上場しすぎて、早く黒字化を目指したからこそ世界に出られなかったMixiと、シリコンバレーのビジネスモデルで、ハイリスク・ハイリターンのお金を集めて世界制覇に行ったフェイスブックの違いで、戦略の違いだから結果が出たんだけど、見ていてすごく勿体無いと思いました。
矢﨑:
どのマーケットに乗っかるか、みたいなことがすごく重要だったってことですか?
田中:
やっぱり、そこは資本主義の成熟度がすごく影響しているんです。僕、先週ダイニーの山田さんにお会いしたのですが、飲食のふりで「今のモバイルオーダーってどんな感じですか?」って伺ったところ、日本にも競合はいっぱいいるんです。でも、彼らはアメリカのKrausとかBessemerとか、すごいUSのVCを入れて、やっていて、「何が違うのか?」って聞いたら、基本的に、見ているベンチマークの対象が、例えば、南米でやってるこの会社はこういうベンチマーク、北米でやってるこのスタートアップはこれをベンチマーク、アメリカの競合のToastというところはこれでやってるから、お前らはこれでいい、みたいなことで、最初からマーケットの定義が決まっているんです。かたや、プロダクトを見れば、レストラン向けのモバイルオーダーで同じようなアプリを作っている会社もあるんだけど、まずそのところは基本的に4人でやっていて、「来季、頑張って黒字化を目指す」ということで、日本のベンチャーが5000万円で、次のシリーズAで3億円調達したいと思っている人と、作っているものは同じでも、最初に定義するマーケットの勝ち幅の大きさが決まっていて、それはやっぱり成熟度による。価値幅で勝った人がいっぱいいれば自分もやろうと思うけど、なかなかそういう価値幅で勝った人がいないと、「野村秀雄がいる前にメジャーしていくか」みたいな話になって、まだ、本当の意味での野茂英雄が日本にいない、というか、メルカリとかスマニューですら、ちょっとムムム、みたいな感じなので、そういうのはダイニーの山田さんみたいな人がやっていて、なんかかっこいいな、羨ましいなと思って、僕はゲームって言うのでやってますけど、所詮ゲームでね、っていう感じで、もっと生活に役立つものでグローバルで勝ちたいな、というのを嫉妬しました。
矢﨑:
ダイニーが出てきましたが、アメリカのBessemerから資金調達するのを目指していたか、などその辺りのお話をお聞かせいただけたらと。
野本:
もともと彼はプロダクトを作るのがただ好きな人で、その中で何回もピボットしてると思うんですけど、モバイルオーダーとPOSが当たって伸び始めたんですよね。そこからこの事業を最大限に伸ばすためには、どういう資本政策が必要かという時に、当然、アメリカの「Toast」みたいな会社をベンチマークして分析すると、めっちゃ赤字を掘ってるんです。利益が出るまでには、まあ相当なキャッシュを燃やさなきゃいけないので、同じように金を多様に集める必要があります。しかし、さっきの成熟性の話ですけど、僕らも含めて日本のVCのお金の総量はそもそもUSと比べると常に足りないので、ファンドサイズがとても小さい。アメリカはお金がたくさんあるから、リスク許容度が高いんですよね。Bessemerから見れば、10億、20億なんて全損しても痛くも痒くもないので、そういったリスク許容度が高い投資家を招き入れて、資本の殴り合いに参入するというのを、今回やったラウンド前の段階で、次回もそういう方向性でいこう、みたいな話になりました。それこそ、マイクロソフトみたいな企業を含めて、ここ2,30年で勝っている企業が巨大なキャッシュを生み出して、それが再投資され、また勝っているという循環の中で、今、スペースXの時価総額が、謎なことに未上場のままで、いわゆる価値のフィードバックサイクルなのかっていうのを、まざまざと見せつけられている、という感覚がありますね。
矢﨑:
当時マイクロソフトにいらっしゃったという意味では、私たちキャピタル側としてはどうしたらいいかという点で非常に不甲斐ない状況ではあります。こういったシンギュラリティ・ソサエティのようなコミュニティーは非常に重要かもしれません。そのあたりのビジョンについて、お聞きしたいです。
中島:
どうだろうね、難しいよね。でも、マイクロソフトは結構早く上場して、そこから大きくなったので、今の市況はかなり違いますよね。だから、さっき裏で話したけど、僕、このスペースXとかに投資したいけどな、なかなか上場してくれないじゃないですか。マイクロソフトが上場した時は、多分マーケットキャップがすごく小さかったですよね。1000億いかないくらいでしたし、そのおかげで上場後に受けたストックオプションがバンバン大きくなって、いい思いをしました。でも、どういう風に今この話を進めようとしているか、僕にも分かんないんですけど、でもやっぱり今は、日本のVCだけでは支えきれないくらいの大きなマネーゲームがアメリカ側で起こっているので、多分、日本VCってのは本当に最初の一段ロケットでしかなく、二段三段はシリコンバレーでガッツリやらないとグローバルで勝負できない、というしかない状況だと思います。でも、それが正しい答えとも言えなくて、僕も自分でその会社をアメリカで起こしてみたんですが、結局VCというのは、100社に投資して、1社が大ホームラン、10社がそこそこでいい、っていうのが基本です。そうすると、VCからお金をもらった後にも、VCからずっと見られていて、その後、成長し続ける会社なのか、捨てられるのか、早めにイクジットしてほしいのか、みたいな選別も起こる。で、CEOとして、ファウンダーとして始めたら、自分は大きなイクジットをしたい、捨てられたくない。でも、そこでジャッジングされて「お前、もう追加投資しないよ」って言われるわけです。そこの、すごい辛い思いを耐える精神力がものすごく必要で、赤字で走るっていうことは、要は潰れる可能性も高くて、VC側としては潰れてもいいんです。だから「お前、金を出したんだからぶっ走れ」って言われ、このベースで人を雇ったら9ヶ月で潰れるじゃん、みたいな状況にも追い込まれる。そこでも、本当は心の底では「あと9ヶ月で潰れるな」って思いながら、自信を持って走り、社員にも自信を持って言わなければならないし、新しいVCにも「まさか、9ヶ月で潰れるなんて思ってない」って隠しつつ、自信ありげにお金集めをしなきゃいけないです。結構辛い思いを僕はしました。僕は結局その2つエクジットしたけど、VCから見るとホームランじゃなくて一塁打、二塁打ぐらいだけど、でもそれでも評価してもらえているので。本当にホームラン狙いで赤字でぶっ続けるっていうことをやった人たちはいっぱいいるけど、そのうちの大半は潰れています。だから、エクジットゲームで言うとどこを目指すか、自分のポジショニングっていう、すごい難しい話になるので、それから考えると、じゃあミクシーは果たして失敗だったのかというと、失敗じゃないのかもしれないし、分かんないですよね。でも、やるんだったらフェイスブックなりぐらいの大きさにやりたいっていうのであれば、潰れる確率8割でもいいから赤字で突っ走るっていう覚悟があるし、ずっとその自信ありげにお金集めしなきゃいけないです。そこは、ものすごく強くなければならなくて、アメリカのVCからお金を集めるとなったら、もう覚悟決めるしかなく、どんなに自分が不安でも、もう一度とも不安そうなそぶりを見せたらいけないんです。それは、社員に対してもお客さんに対してもVCに対してもそうですけど、常にカリスマ性を持ち、自信ありげにお金集めを続けるっていうのが、シリコンバレーなりのCEOのビジネスの続け方なので、時々僕はメルマガで書くんですが、ほとんどの詐欺師とカリスマ創業者は紙一重なので、そこは覚悟してやってください、っていう話です。
矢﨑:
アメリカのVCから資本を入れるというのが、ダイニーの話と今の話と共通していますけど、最初からアメリカの投資家を入れるかどうかというのも大きく違いますよね。支えている日本のマーケットで日本のベンチャーキャピタルを入れてきていると、最初からグローバルなサービスを目指して、例えばアメリカでチームを作って、アメリカでCEOをするということ。リスク許容度やストレスの受け方も多少違うから、その辺は見据える必要がありますが、自分のポジションとして、どの道をたどるのか、という、少しずつロールモデルが見えてきている中で初期から選んでいくという話になるのかもしれません。
中島:
日本人は謙遜をするじゃないですか。あれはいけないかもしれません。謙遜してたらグローバルで戦えないんです。明らかに「この会社はもう軽く1000億の価値がある」と自信を持って言い続けないといけないので、それが言えないとお金が集まらないし、謙遜する日本人という美学は捨てなければならないと思います。
田中:
それはそうですけど、結構ゲーム関係で中国の企業とか見ていると、2種類あると思います。一つは世代的な問題と、今の山田さんとかにしても自信はあるけど、ちょっとわりとナイーブなところも隠さずにいる。中国とかで結構すげえ当ててるバイトダンスの人とかも、わりと物静かなエンジニア風だったし。わりと、いきなり日本人が「イーロン・マスクになれ」って言われても無理ですよ。多分遺伝子的に違うと思うんです。なんかちょっとおかしいじゃないですか、イーロン・マスクとか、僕らとは違う生き物っていうか。昔、世界制覇したホンダとかソニー、任天堂とかがあるので、プロダクトが雄弁に語ってくれれば、本人の押し出しは必ずしも必要じゃない。アメリカでは、その代わりに偽イーロン・マスクみたいなものがいっぱいいるし、ウィワークみたいなことになるわけじゃないです。ネットっていうビジネスは極めてソフトウェアであり、ユーザーベースが大事だし、英語圏が大事です。ネット社会では、そういうのが見えにくいんで、この20年くらい、日本は負け続けて「もう日本人のやり方は全部ダメでアメリカだ」って言われていますけど、今はちょっとディープテックとかハードウェア寄りの世界になったら、昔、日本で勝った時代もあったんで、僕らが中島さんの言う通り、なかなかジョブスとかイーロン・マスクにはなれない、陰キャでもプロダクトがイケててグローバルで売れるっていう勝ち方もあるんです。フィンランドのスーパーセルの人にも会ったことあるんですけど、すげえ陰キャで、まるで「ほんまに金持ってんのか?」って感じだったので、僕ら日本人は世界的に見ても、どっちかというと陰キャだと思うんで、孫さんとか、異常者だと思うんですが、そうじゃない? 陰キャの勝ち方、いいプロダクトで。やっぱり市場の定義が大事だと思うんです。一番取り切った100の状態を、ミクシーは日本の1億人マーケットっていうことでやって、見た世界と、フェイスブックはアメリカの大学から50億のマーケットみたいな世界と、ホンダとかソニーとか、マーケットの定義がバイクとかでかいじゃないですか。日本だけでバイクを売るとか、別にしなくても、アメリカでもアフリカでも売れるわけです、定義の仕方次第で。そういうものづくりも勝てるんで、ダイニーとかは今、東南アジアとか、聞いた感じでは広い飲食マーケットの100%で取るかどうか、っていうことで、陰キャで勝てる、ものが雄弁に語ってくれるようなビジネスを僕らは探すしかないんじゃないかな、と思います。ゲームもそれに向いています。
森:
「盛る」って言った言葉が、多分ちょっと強めになって、強いことで陽キャ、例えばイーロン・マスクっていうのが思い浮かぶんですが、ビル・ゲイツはどっちかと陰キャ系だったと思いますし、別に陰キャ、陽キャとかはどうでもいいんです。多分、見ている世界、どこの世界を見ているかというのが大きいんですよね。その世界の8割を取るのか、別の世界の3割を取るのか、っていうので、その見ている世界がどうなのか、もちろん市場の中の状況が大きいんじゃないかなと思いますし、VCが話すときにも当たり前に「ここ100%信じてる」って盛るから、もちろん盛り過ぎてる人もいるけど、そういうのが溢れてるのは、結構必須条件なんじゃないかなという気がします。
野本:
山田さんの例も出ていますけど、続けると、彼も最初は普通に、身近にみんな使ってもらうプロダクト作るのが楽しい感じで、それが進むにつれて、なんか目標が上がってくるんですよね。よく二人で冗談で話してるんですけど、「資産帳がどんどん上がってくるから、いつも一合目みたいな、ずーっと一合目みたいな感じなんですけど、これ何が違うんですかね」って。その山頂が固定されている人と、どんどん進んでいく中で、見ている世界も大きくなっていく人。なんか、この目線の変化が一個のキーポイントだと思いますね。
森:
それって、結構、スタート時点でその人が持っている「こうなんだろう」っていう固定観念じゃなくて、また基本的に常に満足しない人、つまり、見えるところがゴールだと思っている人と、あっちの方がゴールだと思っている人との違いは結構大きいのではないかと思います。日本では、結構こじんまりしてしまう人は、上場がゴールになったり、日本で有名になることがゴールになって、そこで終わっちゃう、というケースが多い気がします。
中島:
僕は、その目標がどんどん上がっていくというのは、ちょっと違うように思います。やっぱり、始めた時からすでに、すごく先を見据えている人は、見えているし、目指せるものがあると思います。たとえば、これは「火星に人を送る」っていう目線で始めるけど、最初はちっちゃな衛星を打ち上げるだけで構わない。そういう人は、最初からものすごく先を見ていて、作るものは着実に一個ずつ積み上げていくから、外から見るとだんだん目線が上がっていくけど、実はすでにすごい先を見ている。イーロン・マスクであろうと、陰キャであろうと、そういう目線を持っている人は、「人間は火星に行くべきだ」という確信を心の底から持っているので、すごく説得力がある。確かに、上場がゴールになったり、六本木ヒルズにオフィスを構えるとかがゴールになってると、本当にちっちゃいんですよね。そんなやつに投資したくないです。で、日本のベンチャー企業を見ると、本当に「六本木ヒルズにオフィス構えてTBSのアナウンサーと結婚するのがゴールなんじゃねーの?」って思っちゃいます。残念ながら、もしそうなら、絶対こことは合わないので、そうじゃなくて、本当に火星に人を送り込むとか、各家庭に人型ロボットを送り込むっていうのをゴール設定にして、「明日、僕は何やで」っていう、そういうスタートアップ精神を持ってほしいです。そして、その中にたまたま上場する。それは資金集めのために上場するのであって、資金集めが必要なければ上場しなくてもいいんですし、そういう大きな目線を僕は持ってほしいと思います。
田中:
僕は心から中島さんを尊敬しているので、その通りだと思います。その上で、ちょっと話がズレちゃうんですけど、僕はゴルフが好きで、今皆さんゴルフとかおっさんのスポーツをあまり見ないと思うんですけど、なぜか日本の女子プレイヤーがアメリカのUSゴルフでトップの方にめちゃくちゃいるんですよ。僕らでシリコンバレープレイヤーみたいな。それは、ちょっと前は韓国だったんですよ。なんでそうなったかって言ったら、別にシンプルで、そっちでやった方がもうかるからっていう。まず、国内マーケットが元々韓国とか小さいので、韓国で一番になって賞金王で1000万だったら、それならアメリカで100番で1000万もらえた。アメリカ行くじゃないですか、っていう感じで、韓国が先に起きたんです。日本とアメリカの経済成長って、この20年くらい差がついて、日本で一番の人よりも、アメリカの50番の方が同じだったら、「アメリカ行こう」って純粋に経済合理性に基づいて動いていますし、例えばゲームもそうなんですけど、フィンランドなんて、人口200万人しかいないんで、国内向けにやっても、どんだけ勝っても、利益100億の会社なんて絶対作れないんで、出るしかないということです。例えば、日本で一番になって、僕のアプリで一番出ると、年間一千億ぐらいの最大利益が出る可能性があるんで、そこで賞金王を取れば結構美味しいじゃないですか。でも、それがいろんな分野で、日本が世界の市場が大きくなると、日本で一番取るより、アメリカで10番の方がいいとか、そういうことがいろんな分野で起きつつあると思うんですよ。僕はゲームでそれが起きたと思ったんで、日本で一番取るより、アメリカで全然、パブリッシャーとしては100番目くらいでも利益は変わらないじゃないですか。明らかに、1番取るより、100番取る方が簡単だなと思って、要は、大きなマーケットの中で行くっていうことが起きて、今後どうなるか、日本経済成長がどんどん止まって、日本で一番になっても、スタートアップで新興市場で上場しても、マーケットキャップ100億の会社でも、中々難しいってなれば、さすがに僕が20代だとしたら、アメリカで3年くらい、MAで100億で売れてるんだったら、そっちの方が良くない?ってなったら、全員そっちに行き始めると思うんですよ。そっちに行き始めると、やっぱり中には突然変異的に、「俺、100億で売るつもりだったんだけど、アメリカの5年で1兆になって上場できそう」っていう人が出てくると、俺も俺も俺もってなって、気づいたらシリコンバレーに日本人スタートアップがめっちゃ勝ってる、っていう感じです。純粋に、目線が高い、本当って天才的なその人が今でもいるし、それは前提で、今後はそういう風になっていくから、日本の経済成長が、石破総理とかがどんどん間違えた結果、経済が停滞すればするほど、ここじゃ勝っても賞金王になってもしょうがないなと思ったら、自然にも経済合理性で行くしかなくなるんで、そうなると、逆に相手するVCもアメリカのVCと話さなきゃいけなくなる、って感じです。英語じゃなくても、もうAIあるじゃんみたいな、そういう世界になると、壁がなくなって、10年くらいだったら大谷みたいな人が出てくる、僕は30年遅く生まれなかったら、というか、今絶望してます。
矢﨑:
今がその時だな、ということですね。
野本:
日本が破壊されたらいいんですかね。韓国もあれですよね。経済危機で一気にちょっと先にという感じで。
田中:
結構、例えばGendaとかShiftとか、日本の霞ヶ関キャピタルとか、日本の新興市場で、すげーって言われて、みんながベンチマークしている会社とか、やってることなんか、僕、めっちゃ尊敬してますけど、ゲーセンとか土地転がしとか、いわゆる受託構造の中のいわゆる人月商売とかで、そういうのでも5000億とか出てれば、そっちでいいやって思うのは、僕、自然な心理だと思います。そういうのが、成り立たなくなってきたときから、初めての海外勝負になるんでしょう。多分、飲食は知らないので、想像で話すんですけど、飲食向けのモバイルオーダーサービスとか、真面目にやって日本で取っても、日本の飲食だけでやっても、大した規模にならない業界だと思うんです。飲食業界はそんなに、儲かる業界じゃないから、そこ向けにSaaSでやっても、そんなに利が薄いっていうか、だから、僕があったことも、本人も知らないんですけど、そこで賞金王になっても、俺なんか100億の会社になるかどうかも怪しいなと思ったら、もうそこは、なんかアジアンツアー出るしかねぇな、とか、USツアーでやるしかない、っていう風に、スポーツ選手的な感覚で言うと、出たらしょうがないから、アメリカのVCとも話すしかなくなるんじゃないかなって、推測してますけど。
野本:
リクルートもね、まぁ割と飲食中心にやってるんで、まぁ、それないの人ならそこそこ満足できる企業規模、目指せるマーケットだとは思うんですけど、結局、何すかね、欲求の大きさというかタンクの大きさなのかな、その経済合理性に置き直すと、より大きな事業を作ったという話になるし、あるいは、火星に人を送るみたいな、ビジョンレベルで大きいことを考えているか、っていう、どっちかなんですかね。表裏一体かもしれませんが。
田中:
なんかプロアスリートを見ても、メジャーとかの大谷みたいに、心から野球好きで野球をやっている人と、野球をやると一番儲かるから、別にドミニカとかでめっちゃ運動神経よくて、もう別にクリケットでも、なんでもあるけど、野球をやると一番儲かるから野球をやって三冠王なんていう人もいるけど、別に俺、引退したら一切野球に関わりたくないみたいな、ブクブク太るあの人とか、ブラジルのサッカー選手もいくらでもいるじゃないですか。なんか、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、それはもう流派というか、Aタイプ、Bタイプがいて、中島さんはそのAタイプのすごい人も出ろっていう話だし、今僕がやってたのはBタイプもすごい人で、どっちも結局パフォーマンスが良ければ、例があるし、いいんじゃねぇの。どっちかっていうと、僕ら日本人はBタイプの方が、今後現実的にやっていくと思います。例えば、堀江さんとか、本当にAタイプのすごい人だったと思うんですけど、ああいう失敗して捕まったりするのを見ていると、そのジェネレーションは「あんた、堀江さんみたいになるからやめとき」ってお母さんに言われると思うんですよ。だから、そのジェネレーションが、今ある中ではBタイプで、それは一周したらまたAタイプの人が出てくる社会になるんじゃないかなって思います。
森:
今のAタイプ、Bタイプみたいなアナロジーは面白いなと思いました。確かに日本で生活しやすいし便利だし、絶対、これを解決しないと本当に不便っていうのは少ないと思うんですよね。だから、その大きな問題で解決しようなんてなりにくいので、Bタイプというか、逆算して稼ぎたい、稼ぐために、どちらの市場であっても大きくやろうっていう人が増えれば、結果としてグローバルで活躍する人が出てくると思います。同時に、「グローバルで勝てるか」っていう目線で言うと、いくら稼ぎたいからなんとかっていうよりは、「この問題を解決したい」という意志があって、その問題が、たまたま日本にしかなかったものなのか、よく見たら日本でも、世界中でも、何カ国かで解決できる問題だったら、そうやってやろうっていう、入り口が全然違うということなんじゃないかなと。なので、Aタイプ、Bタイプっていうのは両方あるんだろうなって思います。
田中:
結構、身も蓋もない話をすると、実家の太さ問題って最近すごい感じていて、僕の周り、僕49なんですけど、同世代で成功して上場したとか、お子さんってみんな、結構多くの方がアメリカとかにお子さんの中学とかアメリカとかに入れていて、僕らからすると、僕、中学生のときは灘中だったんですけど、日本でいいって言われても、でも灘中に行くっていうのは、今、いわゆるパワーカップルくらいの日本だと開成とか、お子さん、年収2、3000万ぐらいで。上場オーナーの子どもって、だいたいスイス行って、イギリス行って、アメリカ行って、最後にスタンフォードとか行ければいいな、みたいな世代、その子たちは、もう明らかに家に何でもあるし、僕みたいな普通の家の子から出ても、もう見ててむかつくんですよね。最初から裕福だから。その子たちは、多分もう中島さんが言う通り、別にいや、一千億上場して、TBSの女子アナと付き合うとか、いや、もうディフォルトでできてるんですけど、みたいな世代が、もう日本にも生まれてきていて、その子たちは当然、やっていても、周りから1つ抜き出ないから、やっぱりアメリカに行って、僕はネクスト・イーロンみたいな、すげえこと、量子コンピューティングでやりたいとか、そういう風になってくるんだろうなって思うんですよ。だから、そういう点でも僕は日本の今後に関してはすげえポジティブで、そういう子たちが実際、最近会う人も、開成出て、ミシガン大学行って、向こうの教授と一緒に物流のエンジニアとか、このことでやってますとか、あるいはその開成出て、AIやってとか出てきていて、僕の世代にはそんな人見たこともなかったんで、所詮は日本マーケットで賞金王くらいの、例えばメリカリの山田さんとか、関の山というと怒られるけど、普通、山田さんのお子さんの世代はいよいよ、生まれながら六本木ヒルズ、麻布台ヒルズに住んでいたら、次はもっと行くでー、みたいな子供が出てくるから、そういう点でも、ほんと、30年遅く金持ちの子に生まれたら俺だってっていう気持ちです。
中島:
日本のベンチャー企業がなんで海外で成功しないか、あるいは世界で成功しないか、っていう疑問になると、なかなかわからないかもしれませんけど、さっき言ったように、僕はAタイプ、Bタイプの話、結構いいと思ってます。例えば、今だとAIネイティブ、要は既存のビジネスがある人たちがAIを利用して変えようとしても無理だから、ゼロからAIを前提とした新しい企業を作った方がいいっていう発想は僕はすごく思っていて、でも、それっていうことは、結局既存のビジネスを破壊するわけですよ。例えば、AIネイティブの銀行を作るとか、ぜひやってほしいと思うんですけど、多分それを日本でやると失敗するんです。っていうのは、ものすごい抵抗勢力が日本には強いからです。もしAIネイティブの銀行を作るなら、アメリカに行った方がいいです。その要は、Uberは日本じゃ絶対に生まれないです。だってタクシー業界の反対があるんですから。逆に言うと、何がゴールか、本当にTBSのアナウンサーと結婚するのがゴールだったら、日本でやればいいんですが、もしAIネイティブの銀行を作るとか、AIネイティブのタクシー会社を作りたいんだったら、日本でやろうとすると潰されるし、下手すると牢屋に入るので、アメリカに行ってやりましょう、っていう話です。その目線で考えると、ひょっとすると自分はアメリカに行くべきか、日本でやるべきかが見えてくるかもしれません。
田中:
これから、本当に見たことない経歴の人っていっぱいいるんで、お父さんが超金持ちで、お父さんが日本の上場企業の人たちからちょっとアメリカに行って、アメリカでアメリカの友達と起業する、みたいなとかって。もう何か背景が違うっていうのと、あと本当に、中島さんのいう通りで、この国っていまだにね、Uberですらほぼ半永久的に認められないくらいの、だって石破茂ですよ、この国なんか。もう向こうにイーロン・マスクとトランプがやってくるのと、石破茂でもうやっぱり、本当に社会主義対ハイパー資本主義の国みたいな戦いになってるから、国のシステムの問題で、何か世界一になりたかったら、もう早めにアメリカに行くしかないんです。ダルビッシュもね、最初「俺、アメリカ嫌い嫌いや」って言ってたけど、もうあーなると行くしかないっていうか、日本だとまともに勝負してくれないんだよ、みたいな。だから、これからバンバン出ると思いますよ。そういう風になってくると、日本の既存のVCとかは、いわゆるローカル化、今の地銀みたいな立場になりつつあるので、まあ、生き残りどうするかという問題はさておき、その時に見えてくるのは、本当にそういうメジャーに行くチャンスがあるんじゃないか、っていう話です。僕はちょっと、メジャーになんかまたチャンスあんのかなって、年齢的に行けますかね、って感じです。
森:
アメリカは、日本と違って、年齢を全然気にしないんですよ。日本は結構年齢を気にしますけど、アメリカは本当に何歳でも構わないので、何歳でもいけるんじゃないかな。ここの原点に戻ると、その時、今ここで、こう応援したい日本発のものがあれば、たとえばミシガンに行ってもいいんですけど、そこで大学卒業してそのままアメリカで会社を作ったやつは、今、これいける日本初みたいなのに入るのか入れないのか、ちょっと思っているんですけど、それは全然、一つ成功例としてはいいんですけど、そういう人たちに、もちろん出身して成功してもらうというところもありますし…
野本:
日本初とか、考えなくていいんじゃないですかね、っていうのは思います。もう、個々人が最大限自分のビジョンを実現していくという話で。いや、難しくないですか。日本発の定義って、冒頭でもありましたけど、登記の話なのか人の話なのか、帰化した人はどうなのかとか、USでやっている日本人は何なのかとか、そういう感じですし、ソフトバンクグループって、日本の会社なんでしょうか、果たしてみたいな、っていうところもありますし…。
森:
日本の市場よりも、さらに大きい市場を取れるような、もしくは企業価値になるような会社がどう生まれるかってところだと思うんです。
田中:
それも結構一時期考えたことがあって、ちょっと前、例えばソフトバンクにしてもリクルートにしても、今が勝ちパターンで、結局日本ですっげぇドブ板営業みたいな、携帯を売りまくったりとか、いわゆる求人サービスを売りまくってやることで得た、日本のドブ板営業で得たお金で、純粋にインベストっていう形で、アメリカのピカピカの会社を、Yahoo買ったりとか、ARM買ったりとか、リクルートだとインディードとか、アメリカの資本という形で買ってやるパターンしかないんです。例えば、日本の田舎の地主が、ビジネスセンスとかはないけど、地主でお金持ってるから、東京に行って銀座とかにピカピカのお店を出して、金の力で買う、みたいな勝ち方だったんですが、ようやくリテラシーが上がってきて、その時の地方が今の日本みたいな感じで、東京がアメリカみたいな感じで、そこで勝負する人たちが、本当に意味で出てきたんで、日本発とかあまり考えなくて、日本人起業家で、だってアメリカにもGAFAとか、ロシア人とかですもんね。セルゲイ・ブリンってロシア人ですよね。ジョブスはシリア系移民のアメリカ人とか、基本的にみんな移民の子供なんで、そういう日本系アメリカ人とか、もうありっていうんですければ、これから30年くらいは、スタートアップ界の大谷みたいな人は、何個か間違いなく出るんで、ちょっといいなーって思います。
中島:
せっかく田中さんがいるので思うんですけど、やるんだったらAIネイティブなオンラインゲーム作って欲しいです。
田中:
どうせもう次やるんだったら、別にゲームにこだわることなくて、AIネイティブに、既存の純粋な、普通の社会的インフラみたいなもので、完全にAIネイティブできることが、まだ間に合うことがあるんだったら、それを探す。なんか、ちょっと、ゲームはもう割とAIネイティブって言っても、そのさっきのAIの銀行みたいなことのほうにすげえ今興味があるっていうか、僕にバックランドがないし、できるのか分からないですけど、まあ、別になんかカードゲームとかリソース管理とか、アカウント管理とか、銀行と変わらないんじゃないかって思ってる気持ちもあるんですよ。ぶっちゃけ、そのゲームの中でも資産があって、今日はアカウントがあって、それぞれのセキュリティとか、ちょっともっと強度がいるんだろうな、とか、そういう感覚があるんですけど、やってることが、ぶっちゃけゲーム作るのと変わらないんじゃないか、って感じです。どうせやるんやら、そういうことでやってみたいって思ってます。今、勉強してるんですけど、ちょっとこの知見を貯めてるんですけど、っていう感じです。
中島:
間違いなくAIは人間を置き換えるでしょう。だから、大量に人間を雇わないとできないビジネスが、今いっぱいあるんで、そこをガサッと見て、例えば、10万人とか社員を抱えている会社って、AI導入したら、10万人切れないじゃないですか。そこに、一人で、AIを抱えて切り込む。
田中:
銀行とか、本質的に情報処理だから、100人くらいできそうです、30人とかにできるんじゃないかとも思います。
中島:
だから、その辺りをちょっと、という。
田中:
わかりました。勉強になります。
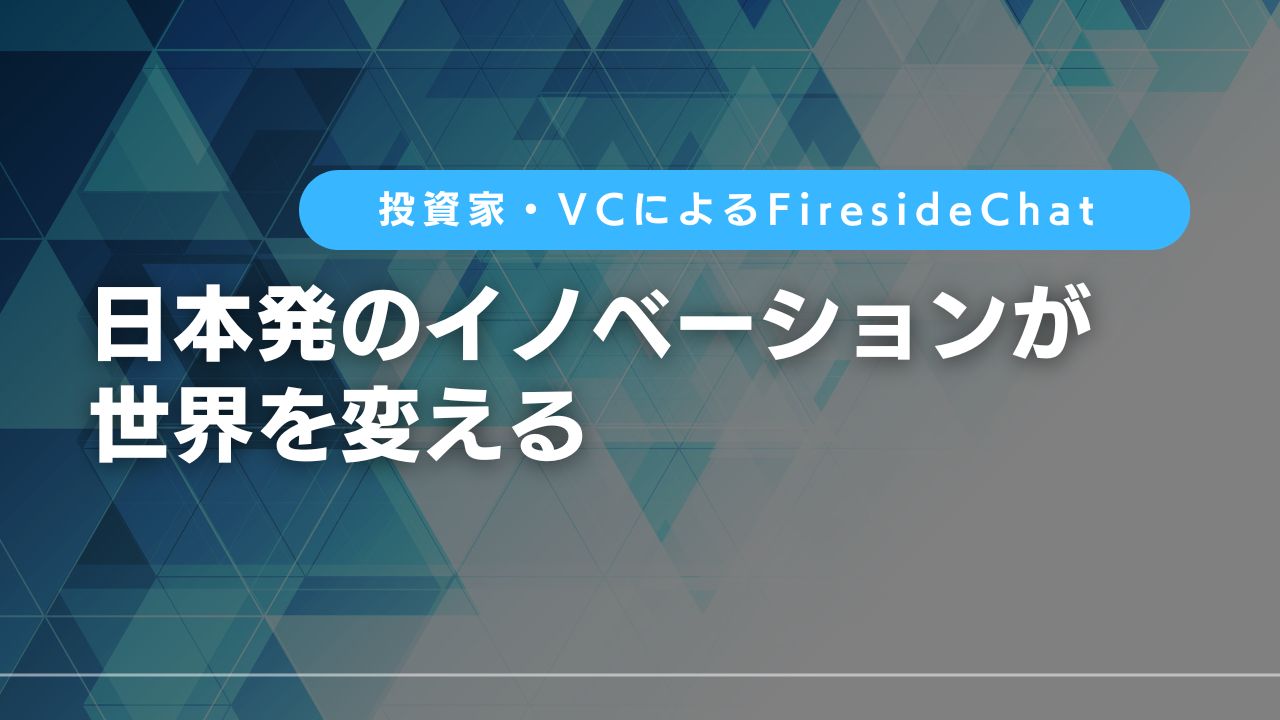



![書評:LangChainとLangGraphによるRAG・AIエージェント[実践]入門 (エンジニア選書)](/images/articles/blog/2024/11/langchain-graph.jpg)