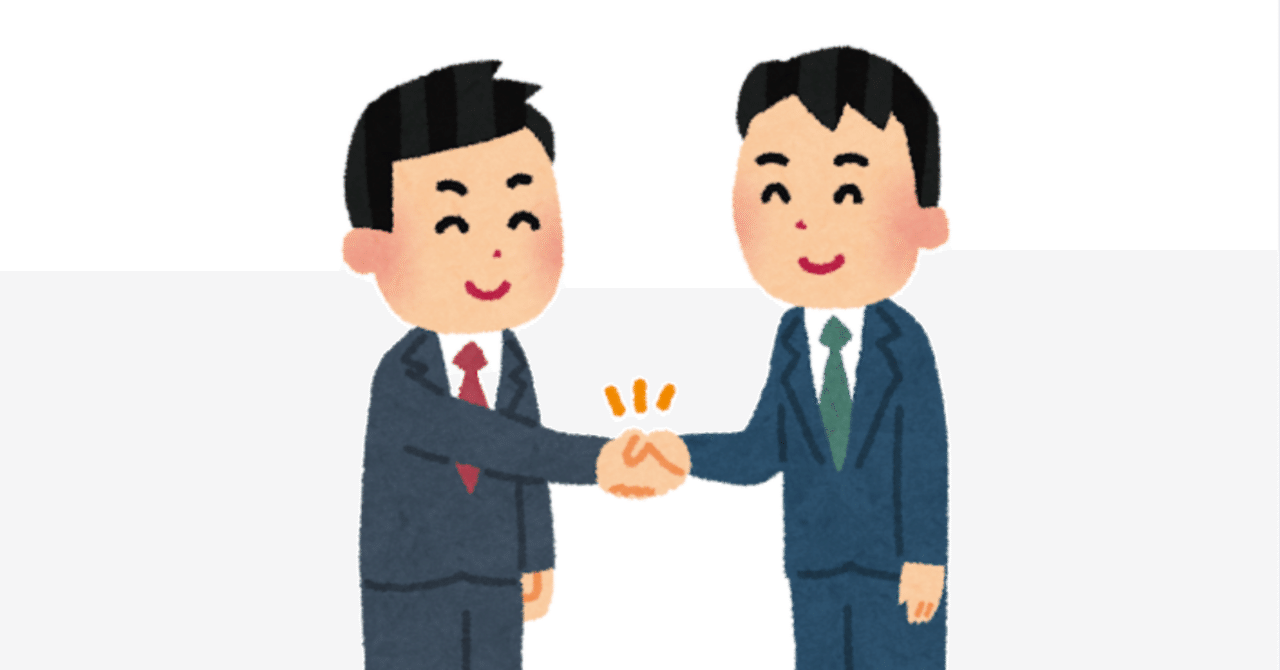すべての企業が“スタートアップ”を目指すべきではない。成功の定義は、資金調達と成長スピードにより大きく異なる。
国内外で「スタートアップ熱」が高まっている。新たな技術、新たな価値観を背景に、起業の裾野が広がるのは歓迎すべき流れだ。しかし、スタートアップと中小企業の違いを理解せずに語られることも少なくない。とくに、「スタートアップ=ベンチャー=中小企業」という単純な認識は、起業家自身にも、投資家にとっても大きな誤解を招く。
ベンチャーの定義──成長か、撤退か
ベンチャー企業とは、その本質において「急成長を前提とした存在」である。選択肢は2つしかない。「成長するか」「閉じるか」だ。
成長とは、初期段階であれば年率200%以上、一定規模に達しても年率40%前後の成長を維持することが求められる。こうしたスピードを実現するためには、収益性よりも成長性を優先し、資金を“燃やす”ことが当然視される。この「キャッシュバーン」は、VC(ベンチャーキャピタル)の支援を前提とした戦略であり、持続可能性よりも、圧倒的なスケールを追い求めるための手段である。
VCの役割──成功率ではなく、リターン率に賭ける
スタートアップに資金を供給するVCもまた、この“成長前提”を共有している必要がある。数十社のうち1社が“千倍”に化ける可能性に賭け、その1社で他の失敗を補う──これがVCに求められるリスクテイクである。
もし、「100億円を入れて、3倍のリターンが出れば十分」という思考であれば、それはVCではなくプライベート・エクイティ(PE)や一般的なファンド運用に近い。ベンチャー投資においては、「潰れて当然、その分、化ける芽にこそ全力支援する」という哲学こそが本質だ。
起業家の覚悟──受けるなら“逃げ道”はない
だからこそ、資金を受ける起業家の側にも強い覚悟が必要となる。外部資本を受けた瞬間に、その会社には「急成長」というただ一つの選択肢しか残されない。
「仲良くやる」「会社を維持できればいい」といったスタンスは、もはや許されない。むしろ、「5年以内に時価総額1000倍」を狙うほどの強烈な意志と行動力が必要になる。これがスタートアップ経営のリアルであり、醍醐味でもある。
すべての企業がスタートアップである必要はない
一方で、このような急成長モデルがすべてのビジネスに適しているわけではない。持続的な収益性を確保し、ゆるやかに成長しながら地域や業界に根ざす経営もまた、重要な経済活動である。
自己資本だけで運営し、外部資金に依存しないスモールビジネスモデルは、自由度が高く、経営者の裁量も大きい。そもそも、企業の優劣は「成長率」で決まるものではない。自らのビジョンとビジネスモデルに応じた最適な資金戦略と成長曲線を描くことこそが、経営者に求められる判断だ。