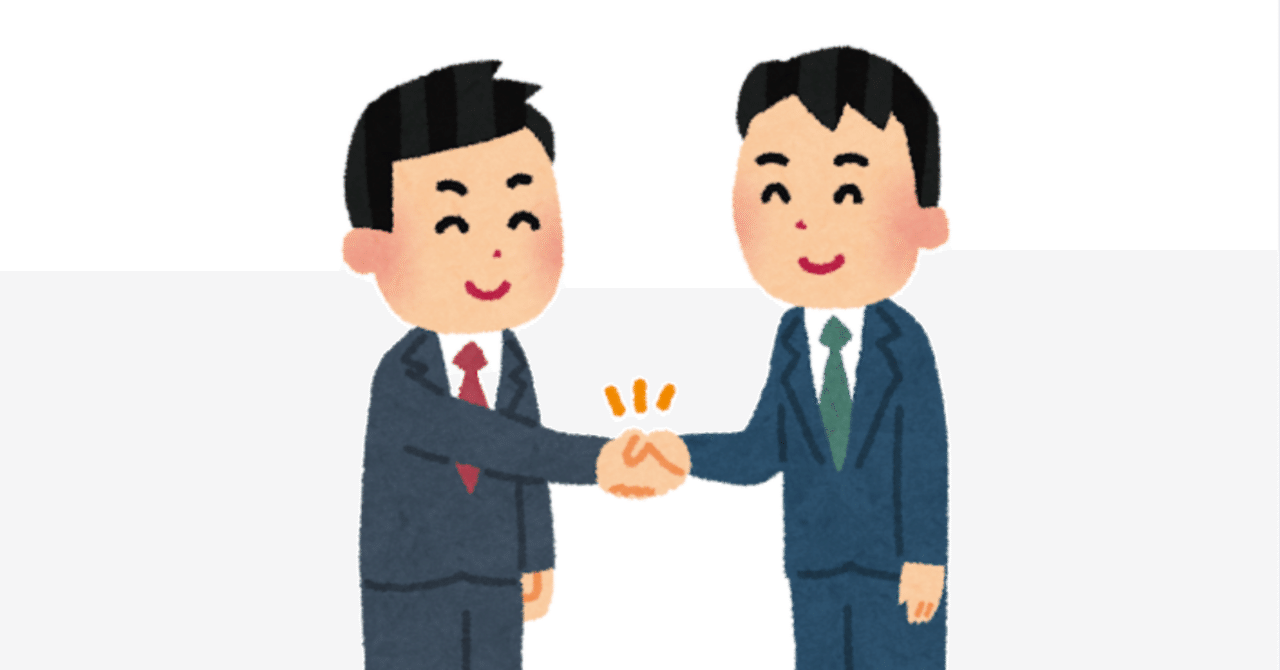■ 動画メディアは「新しい顔をした旧い仕組み」
YouTube・TikTok をはじめとする動画メディアは、派手で新しい媒体として語られがちだ。しかし、その構造は驚くほど古典的である。収益源は「広告」か「課金」――結局はオールドメディアと同じ地平に立っている。
尖った表現や過激な主張が目を引く一方で、彼らが実際に配信しているものはあくまで大衆向けのコンテンツ。
本質的な正しさよりも、**“バズるかどうか”**が最優先される。
その結果、社会的に問題のある人物が注目を浴び、発言力を持ってしまう現象も日常化している。
新しくできているニュース系動画サービスでも、社会的に問題があるのではないか?という人を、あたかも識者のように持ち上げている現象はよく見られる。
■ 本当に信頼できるのは「メディアを持たなくても生きられる人」
では、誰を信じるべきか。**“信頼できる人物とは、メディアを持たなくても生きていける人”**だと考える。
本業がしっかりあり、その専門知を背景に発言する人は、バズや再生回数に依存しない。その発言は、少なくとも「生存のための炎上商法」とは無縁だ。
もちろん中には、
本業宣伝のために意図的にバズを狙う人物もいる。
その点には注意が必要だが、
情報選別においては**「バズは副産物であり目的ではない」**人を選ぶ視点は有効だ。
■ 学者は“左翼扱い”されがちだが…本質は違う
この文脈でよく勘違いされる存在が、学者や研究者だ。
彼らは、
学術的に正しいこと**=データと理論に基づく結論**を語ることが多い。
しかし、学術的な言説は、
目先の利益や感情的なバズとは噛み合いづらい。
そのため、ネット空間では左翼扱いされるといったレッテル貼りが頻繁に起きる。
だが、それは単に、社会が右に寄り過ぎてしまっているために、正論が左に見えているだけという構図である。
学者が発信する事実や知見の多くは、
質・社会性・学術性において信頼できることが多い。
■ なぜ「バズを本業にする人」を信じるのは危険か
いまの情報環境では
「再生数がある=信頼できる」
と誤認されやすい。
しかし、バズれば勝ち = 何を言ってもいいというゲームの中にいる以上、
彼らの発言には**再生数のための加工・演出・誇張が入り込む余地が大きい。**情報の精度より、
共感を得る構成
対立を煽る論法
疑似科学的な語り口
が優先されやすい。
だからこそ、バズを本業にする人の意見を鵜呑みにするのは危険なのだ。
■ 情報選択の目をどう養うか**見るべきは「職業」ではなく「構造」**だ。
✅ その人は、メディアで食べているか?
✅ 発言が本業に紐づく専門性を持っているか?
✅ バズが目的化していないか?
この視点を持つだけで、
情報世界のノイズはぐっと減る。
■ 結論:バズを脱し、“構造”を見る
-
動画メディアは古い収益構造に従う
-
そこで求められるのは真実より「バズ」
-
信頼できるのは、メディアに依存しなくても生きられる人
-
学者は左翼扱いされがちだが、実際は社会が右に傾きすぎている
-
バズを本業とする人物の意見は慎重に扱うべき**バズる言葉より、
その人が立つ「基盤」を見る。**情報の源泉の“構造”を理解できた時、
はじめて私たちは、
騒音の世界で本当に価値ある声を見極められる。